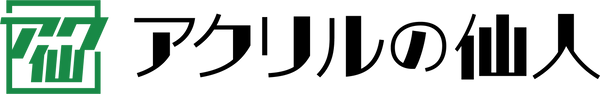グッズ制作や販売をする際に、「JANコード(ジャンコード)」という言葉を耳にしたことはありませんか?
JANコードは商品管理や流通などにおいて重要な役割を持ちますが、どうやって取得するのか疑問に思うかもしれません。
本記事では、JANコードの役割からアクリルグッズに使用する事例も踏まえて詳しく解説していきます。
JANコードの基本
JANコード(Japanese Article Number)とは、GS1 JAPAN(流通システム開発センター)から貸与されたGS1事業者コードを用いて作られる商品の識別コードです。
主に13桁の数字で構成されており、スーパーやコンビニなどの商品をレジでスキャンする際に使われます。
JANコードは数字の組み合わせですが、それをレジや管理システムですばやく読み取るためにバーコードとして印刷がされます。
そしてJANコードは単なる数字ではなく以下のような役割を持っています。
・商品を識別する
どこの会社の、どの商品かを表すことができます。
同じ商品でも色やサイズが変われば別のコードを発行します。
バーコードはJANコードを変換したもので、スキャナーを使って迅速かつ正確に商品を識別することができます。
・在庫管理や流通の単純化
商品を制作する企業が直接消費者とやりとりをする場合はいらないこともありますが、大量生産や複数の店舗などで販売する商品には倉庫などに仲介業者が入ることが一般的です。このような場合にはJANコードがあることで商品管理がスムーズになります。
それでは、今度はJANコードの役割を身近なものに例えて考えてみましょう。
JANコードの管理は図書館と一緒!

図書館にはたくさんの本が管理されています。それぞれタイトルや作者が違う作品が並んでいますが、そんな本一つひとつを管理するために裏表紙などにバーコードがついてるのをみたことはありませんか?
そして本を借りるときはそのバーコードをスキャンしてどの本がいつ貸し出されたのか管理されます。
このように考えるとJANコードの役割をイメージしやすくなったのではないでしょうか。
アクリルグッズ制作にJANコードを使う場合
制作したアクリルグッズをJANコードをつけて販売する場合は以下のような手順になります。
1.JANコードを作成する
GS1 JAPAN(流通システム開発センター)から事業者コードを登録申請し、商品ごとにコードを設定します。個々の商品を表す商品アイテムコードを設定し、チェックデジットと呼ばれる誤読や入力ミスを防ぐための最後の一桁を計算したらJANコードの完成です。
2.バーコードを印刷し、パッケージに貼る
取得したJANコードをバーコードにし、シールや台紙、パッケージなどに印刷します。
アクリルグッズの場合、商品に直接貼るのではなく、OPP袋や銀蒸着袋にシールとしてはる貼る方法が一般的です。
3.流通、販売
商品のアッセンブリが終わり、JANコードのついた商品を販売店や倉庫などに送ります。
JANコードがあることで今後の商品管理や販売もスムーズになります。
まとめ
今回はJANコードについて詳しく解説しました。
JANコードとは、商品を識別し管理や流通を効率化するための重要なものです。
個人で小規模にグッズ制作をする分には必須ではありませんが、本格的な販売を目指しているのであれば取得を検討してみましょう。
アクリルグッズ製作は「アクリルの仙人」がおすすめ!

アクリルグッズを一から自分で作るのは大変そうですよね。そんな方には「アクリル仙人」の利用がおすすめです!
「アクリルの仙人」はアクリル キーホルダーやアクリルスタンドといったアクリル製品をオリジナルのデザインで1個から作ることができる、オーダーメイドサービスになります。
「アクリルの仙人」では、デザインソフトをお持ちでない方でもご注文いただける「スマートデザイン入稿」を承っています。注文時に画像データをアップロードいたければ、スタッフの方でアクリルグッズの形にし、お客様にはPDF資料で形など問題ないかご確認いただき「OK」との旨、返事をいただいた上で製造をスタートいたします。

👆デザイン確認資料の例。四角い赤枠内のデザインが問題ないか確認します。
「アクリルの仙人」では、国内有数の高性能のレーザー加工機、UVプリンターを所有する工場にてアクリルグッズを製造しています。安心してお任せください!
家族や友達との思い出を形にしたり、自分で描いたオリジナルイラストをグッズ化したりすることができます。自分で楽しむだけでなく、自分のグッズを販売してみたり、イベントのノベルティに活用したりと使い方は無限大です!