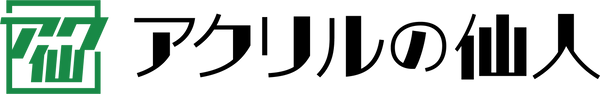推し活・サブカル界隈で使われる「お迎え」という言葉。 特にぬいぐるみやフィギュア・アクスタなどのグッズを購入する際によく使用されるこの表現には、完全に「購入」以上の意味が込められています。
では、「お迎え」の意味や背景、そして関連する文化について詳しく解説していきます。
「お迎え」の基本的な意味
「お迎え」とは、ぬいぐるみやフィギュアなどのグッズを購入することを指す表現です。 単に「買う」「購入する」という言葉ではなく、「家族のように大切な存在を迎える」という意味合いを持つ言葉として使われています。
この言葉が使われる背景には、グッズを単体商品としてではなく、一つの生命や人間を持った存在として大切に扱いたいという気持ちが込められています。
お迎えの文化的背景
この「お迎え」という表現は、日本の「物を大切にする」という文化観と、アニメやゲームのキャラクターへの愛が着いていて生まれた独特の文化です。
特に「つぶらな瞳で見つめてくる」ぬいぐるみや、「生きているように精巧に作られた」フィギュアに対して、単なるモノ以上の存在価値を見るファンの気持ちが、この言葉の広がりにつながっています。
お迎えの流れ
お迎えには、一般的には以下のような流れがあります。
事前準備の段階では、商品の情報収集や、置き場所の確保、予算の計画などを行います。特に人気商品の場合は、発売日や予約開始日のチェックが重要です。
ご購入の際は、商品の状態をしっかりと確認します。 特にぬいぐるみの場合、縫製の具合や汚れがないかなどを丁寧にチェックします。
「お迎え」後は、会場の様子を写真に残したり、SNSで報告したりする方も多いです。これは喜びを共有するとともに、大切な思い出として記録を残す意味もあります。
お迎え後のケア
お迎えしたグッズは、大切に扱うことが基本です。 直射日光を避け、適度な温度と湿度が保たれる場所で保管しましょう。
ぬいぐるみの場合は定期的なブラッシングや、必要に応じた洗濯を行います。フィギュアやアクスタの場合は、ほこりを防ぐためのケースの使用や定期的な清掃が推奨されます。
また、思い出作りの手書きとして、写真撮影や日記をつけるなど、お迎えしたグッズとの日々を記録として残す方も増えています。
SNSでお迎え文化 #お迎え報告
SNSの普及により、お迎えの報告や記録を共有する文化がありません。「お迎え報告」というハッシュタグとともに、出店の様子や設置場所の写真を投稿する形が一般的です。
同じ商品をお迎えしたファン同士で感想を共有したり、ケア方法について情報交換したりする場としても活用されています。
お迎えする際の注意点
お迎えを検討する際には、いくつかの重要な点に注意が必要です。
まず、予算管理は重要です。特に複数のグッズを同時期に発売する場合など、計画購入を心がける必要があります。
また、収納スペースの確保も大切です。 特に大型のぬいぐるみや、コレクション性の高いフィギュアシリーズの場合は、十分な設置スペースを確保することが推奨されます。
まとめ
「お迎え」という言葉には、単なる「購入」以上の特別な意味が込められています。大切なキャラクターやキャラクターグッズと、より深い絆を築くためのキーワードとして定着しています。
「お迎え」を通して、推しとの新たな思い出を作り、大切な存在としての関係を重ねていくことができます。
アクリルグッズ製作は「アクリルの仙人」がおすすめ!

アクリルグッズを一から自分で作るのは大変そうですよね。そんな方には「アクリル仙人」の利用がおすすめです!
「アクリルの仙人」はアクリル キーホルダーやアクリルスタンドといったアクリル製品をオリジナルのデザインで1個から作ることができる、オーダーメイドサービスになります。
「アクリルの仙人」では、デザインソフトをお持ちでない方でもご注文いただける「スマートデザイン入稿」を承っています。注文時に画像データをアップロードいたければ、スタッフの方でアクリルグッズの形にし、お客様にはPDF資料で形など問題ないかご確認いただき「OK」との旨、返事をいただいた上で製造をスタートいたします。

👆デザイン確認資料の例。四角い赤枠内のデザインが問題ないか確認します。
「アクリルの仙人」では、国内有数の高性能のレーザー加工機、UVプリンターを所有する工場にてアクリルグッズを製造しています。安心してお任せください!
家族や友達との思い出を形にしたり、自分で描いたオリジナルイラストをグッズ化したりすることができます。自分で楽しむだけでなく、自分のグッズを販売してみたり、イベントのノベルティに活用したりと使い方は無限大です!